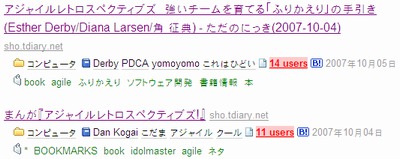2007-10-06(土) [長年日記]
■ 「かぐや」を応援しに行く
ハイビジョンカメラで美しい地球の姿を撮り、続いて一昨日にはついに月周回軌道に入った、日本の月探査機「かぐや」。その管制は(当然ながら)相模原から臼田の64mパラボラを経由して行われれている。ならば(以下略)。なお、ツーリングの模様はふらっとツインにて。

同じアンテナを何度も見に行ってどうして飽きないのかと思われるかも知れないが、今日なんて、山側に微妙に傾いた、今まで見たこともないアングルを見せてくれてるわけ。くーっ、これが萌えずにいられるか!
いちおう、今日の月は深夜に昇って昼過ぎに沈むところまでは調べて来たので、午前中に着けばおそらく管制中だろうと思うんだが、なにせいま宇宙には「かぐや」だけでなく「はやぶさ」もいるわけで、いったいどんな管制スケジュールになっているのかわからない。アンテナが指している先に月が出ていれば確実なんだけど、出発時に晴れていた空がなぜかこの時だけ雲に覆われていて、まるでどっかの映画のタイトルのようなアリサマ。
まぁ、じっくり見ていると、じりじりと動いているのは確かだし、何かを管制中なのは間違いないのでヨシとする。パラボラウォッチをするにあたって、こういういい加減さは大切だ(嘘こけ)。
ところで、アンテナだけでなく、臼田の施設に大きな変化が起きていることは報告せねばなるまい。


左は門を入ってすぐ右手、草っぱらの一部が造成中。周囲にコンクリブロックを並べていたので、おそらく見学者用の駐車場を作っているのだろう。まぁ、もっと早くに作られていてしかるべきだったが、今までのように草の上に愛車を置いてアンテナとツーショット……というわけにいかなくなるのは残念だなぁ。
右の写真は展示室の左側、受付のあった部分が取り壊されている。現在の受付は門寄りにプレハブを建てて仮住まい。どうなるんだろう。しかしなんだ、これって「かぐや」効果? 確かに最近、ちょっと見学者が増えてるような気がするが。

大口径パラボラアンテナで月を狙うという話と言えば、『THE DISH』(邦題「月のひつじ」)。登場するのはアポロ11号の月面着陸を中継したオーストラリアのパークス天文台のアンテナで、奇しくも臼田と同じ直径64m。40年近い年月を経て、今度は日本の64mが月を狙っているなんて、感慨深いじゃあーりませんか。
参考
- 臼田宇宙空間観測所への行き方 - 臼田に行ってみたいと思った人のためのガイド
2007-10-04(木) [長年日記]
■  アジャイルレトロスペクティブズ 強いチームを育てる「ふりかえり」の手引き(Esther Derby)
アジャイルレトロスペクティブズ 強いチームを育てる「ふりかえり」の手引き(Esther Derby)
翻訳者の「角征典氏(a.k.a kdmsnr氏、児玉サヌール氏)」*1から献本いただいた。昨日のネタは別にしても、おれもこのタイトルはひどいと思っているわけだが、良い本はまず褒める主義なのでまずは褒める。
どんな本かと言うと、「アジャイルなソフトウェア開発チームに、効果的なふりかえりを導入するための手引き」になる。アジャイル開発にはさまざまなメソッドがあるけれど、短いイテレーションを上手に回していくためには、PDCAの輪を閉じる「ふりかえり」についても手法を整理しておいた方がいい。
これって別にソフトウェア開発に限った話じゃなくて、例えばおれは今、Webサイト運営チームをいくつか抱えているんだけど、週単位で更新するようなサイクルで動いているから、サイクルの切れ目にふりかえりを入れるのはいいことだと思う。サイクルが短いから、ふりかえりも効率的に短時間でやりたい。そのためには先人の知恵を上手に使おうね、ってことだ。
本書に書いてあることは、端的に言うと以下の2点:
- 「ふりかえり」の「司会」に必要なスキル
- 「ふりかえり」の「パターン」カタログ
「ふりかえり」の「司会」に必要なスキル
ふりかえりのスタイルとして、机なしで椅子を半円形や円形に並べて行おう、と書いてある。で、司会はその焦点に位置しないで(=主役にならない)で、ちょっとずれた場所にいる。これは教師のポジションだ。ふりかえりの司会には、教師と同じスキルが必要になる。……と明確に書いてあるわけではないけれど、本書に出てくる良い司会役は、良い教師像に重なる部分が大きい。
といっても、教室で大勢を前にぼそぼそ喋る日本の教師像ではなくて、我々も映画やドラマでおなじみの、欧米の小規模なゼミをうまく仕切っている教師像だ。あくまで参加者を主役として、何かを押し付けるでなく、全員に何か新しいものを持って帰ってもらう、そんな理想的な教師の持つスキルと同じものが、ふりかえりの司会には必要だ。
正直、ここに書かれているとおりの司会をやろうと思ったらかなりハードル高いと思うんだけど、こういうイメージを抱いておけば、どこに近づけばいいかわかりやすい。かなり最初の方で参加者の感情に留意するよう促されるんだけど、教室に漂う感情の流れをコントロールするのは、教師が真っ先に会得すべき能力だよね。
「ふりかえり」の「パターン」カタログ
本書の大半はこのカタログである。そう、みんなが大好きなパターンランゲージですよ。ふりかえりで使える手法(本書ではアクティビティ……これも日本語化すべき用語だ)に、名前をつけ、分類・整理し、共有する。ソフトウェア開発のさまざまな場面で登場しているパターンランゲージが、ここにも上手に使われている。
これがパターンでなくて単なる事例集になると、応用が利かなくて役に立たない。パターンのレベルまで抽象化されているから価値があるのだ。ただのハウツー本だと思って手に取ると肩透かしに思うかも知れないが、それは読み方が浅い。
もっとも、いくらパターン化してあるとは言っても輸入品なので、日本では使えそうにないものも少なくない。「こんなの絶対みんな引くって」と思えるアクティビティもある。それはそれでいいだろう。自分たちにマッチする手法を見つけて、パターンカタログに追加すればいいのだから。
でもまぁ、カタログってぇのは見ているだけでも面白い。「Mad Sad Glad」を見て「あぁ、あっちの人には"喜"と"楽"の区別がないのか」と気づいたり(日本では「喜怒哀楽」にした方がわかりやすいだろう)。「5つのなぜ」などは日本でもKAIZENの現場では随所で使われれているけれど、「アイデアを出す」ことを目的にするというのはあまり使われない視点だと思った。新鮮だ。
翻訳について
アジャイルコミュニティは伝統的(?)に、いい用語を発明する才能が集まっていると思うんだ。「バーンダウンチャート」みたいにカッコイイのから、「ニコカレ」のようにユーモラスなものまで、名言ならぬ名用語には事欠かない。自分たちの血肉にしようというモチベーションが、こういう言葉に対するこだわりを呼んでいるんだと思う。
「ふりかえり」はその最たるものだろう。「レトロスペクティブ」なんて舌をかみそうな英語を、端的で美しい日本語にずばり翻訳して、その意味までをも完璧に写し取っている。あえてひらがなにしている点も含めて、これはもう、奇跡に近い。にもかかわらず、そしてまえがきやあとがきで日本語訳として「ふりかえり」を使うと宣言までしておきながら、本文中ではいっさい使わないという謎の方針。なんてもったいない。ありえない。
あと「ファシリテータ」もひどい用語だ。上ではあえて「司会」と書いたけど、おそらく「司会」は「ファシリテータ」の持つ意味を完全に表現していないから避けたんだろう。でも言葉なんて使ったもん勝ちだよ。定着してしまえば意味なんてあとから変わるんだから。「ぶち切れ」「これはひどい」みたいな現代用語をさりげなく取り込むセンスがあるんだから、こういう重要な言葉にももっと大胆な決断をして欲しかったな。
「アジャイルレトロスペクティブズ」という書名についても言うまでもなく。ただこれは、NGを出さなかった編集者にも責任があると思う。萌え系の表紙をつけたら魔法モノのラノベと間違われそうなタイトルで、本当に届いて欲しい人たちの目を引くと思うか? おれなら、たとえダサくても、副題の方をタイトルにするね。
……というわけで、ちょっと大胆さに欠けるという点を差し引けば、平易で読みやすいよい翻訳だと思う。日本のアジャイル界には、どんな良書もひどい日本語訳にしてしまう恐怖の集団がいるので、本書のような良い本がその毒牙にかからなくて良かったよ。
 アジャイルレトロスペクティブズ 強いチームを育てる「ふりかえり」の手引き
アジャイルレトロスペクティブズ 強いチームを育てる「ふりかえり」の手引き
オーム社
¥2,640
*1 挟まってた紙に本当にそう書いてあった。名前が多いのも考えものだ。yomoyomoさんもこれ以上変なペンネームを考えるのをやめた方がいい。